 連載
連載
作り手による文章の世界
みちくさドライブ
松塚 裕子
ノスタルジック・芋ロード
2020.11.20歯医者からの帰り道、あたりはもう薄暗くなりはじめていた。
西の空だけぼうっと明るい。
昼間の暖かさがうそみたいに、冷たい風がひゅうっと首もとをすり抜けていった。
うっかり薄着で出かけてしまったことを後悔しながら自転車のペダルを踏みこんで家への道を急ぐ。
治療した歯がまだむずむずしていたし、夕飯の支度もしてこなかったし、なんだか気持ちが急いてざわざわとしていた。
いつも行くにぎやかな公園にはもうだれもいない。
遊具だけがぽつんと寂しげに佇んでいるのを横目に通り過ぎたあたりで、夕暮れの冷えた空気にまじってなんとも言えない香ばしいにおいが鼻をかすめた。
そのにおいをかいだ途端、懐かしさとともに嬉しいような泣きたいような思いがこみあげてきた。
これは、枯れた枝や葉っぱを燃やすときのにおいだ。
どこかの畑で野焼きをしているのだろう。
突如として、私は見慣れた風景の中でひとりタイムスリップしたような気持ちになっていた。
私の育った家には小さな裏庭があった。
となり近所とは程よく距離があるし、裏は崖のような塀があり、ちょうどそこだけがすっぽりと囲われた空間になっている。
焚火好きの父はよく庭仕事で出た枝や葉っぱを乾燥させては、その裏庭で燃やしていたのだ。
当時中学生だった私は年ごろで、なんだか面倒くさい思春期ならではの人間関係に窮屈さを感じながら学校に通っていたように思う。
ほんとうにこんな量必要なのかしらと疑問に思うほどの教科書や資料集、ノートに加えて、変な蛍光色の学校指定ジャージを詰め込んでぱんぱんになったバッグの重みが、肩にずしんとのしかかる。
おなかすいたなあと思いながら夕暮れ時の家の前の坂道をえっちらおっちら上ってゆくと、香ばしいにおいが漂ってくる。
家に着く前から、ああ今日は父が焚火をしているな、と気づくやいなや早足になったものだ。
焚火の日は焼き芋をするのが定番で、夕方くらいから燃やし始め、火が落ち着いた頃にアルミホイルに包んださつまいもやじゃがいもを灰のなかに潜らせてしばし待つ。
そういう日、母はたいてい豚汁を作っていて、芋と豚汁がその日の夕飯になるのだった。
肌寒い中、火を見ながら芋をつついたり豚汁をすすったりしていると、心にどんよりとのしかかっていた曇ったものが消えてうすくなっていくようだった。
あたりが真っ暗になって焚火も終盤にさしかかるころ、白っぽく姿を変えた木片を火ばさみでつき崩して広げるようにすると、細かくなった最後のかけらが星のようにちかちかと燃えた。
それはどこかの町の明かりを空から眺めているようでもあったし、宇宙にひろがる天体のようにも見えた。
その小さな灯が消えるまで、ぼんやりと見ているのが好きだった。
目の前に見ているものが、自分が今生きている世界からは遠く離れたところにある景色のようで、そう感じることで日常に漠然と横たわる不安を紛らわしていたのかもしれない。
中学校は最後まで好きにはなれなかったけれど、大人になるにつれて楽しいこともやりたいことも増えて、煩わしさに気を揉んだ思春期の人間関係も、あの頃焚火を見つめていた時間も、すっかり遠くへ忘れ去られてしまった。
寒い中家路に急ぐ気持ちが、あの頃の私を呼んだのだろうか。
すっかり暗くなった帰り道に家々の明かりが灯る。
昔の小さな記憶がぽつぽつと浮かんでは暗闇の中へ消えていった。
母が初めてパンを焼いた日、あんパンを詰めこんだ袋を抱えて公園で待つ友のもとへ走ったこと。
パンは、まるで小さな生き物のように温かく湿っていて愛おしさに満ちていた。
学校帰り、テーブルにどんと置かれた大きな長方形のアップルパイ。
さつまいもがごろごろ入った鬼まんじゅうが、湯気と共に蒸し器の中に並ぶその姿。
寒い日の記憶はいつも美味しいものと共にある。
誰かから手渡されたあたたかいものは、ずっと消えずに小さな灯りのように残ってゆく。
きっと私は昔も今も、胸の中に大事に持っていたくなるようなものごとに触れていたくて、手を動かして日々を生きているのだと思う。
子どもと過ごすようになってからは、自分でも忘れていたような小さな記憶が蘇ることも多く、幼い自分と今の自分を行ったり来たりするような不思議な時間軸の中にいる。
そのたびに、人の細胞内に眠る記憶の量に驚かされる。
忘れてしまいたいことは、うすぼんやりと、そして幸せなことはその時着ていた服の柄まで覚えていることもあるのだから、都合よくできているなあと笑ってしまう。
いずれ消えゆくこの体の細胞ひとつひとつに、できることなら美味しくてあたたかな記憶をぎゅっと詰め込めこんで抱えてゆけたら、と思う。
友人からさつまいもをもらったので、大きな蒸しパンを作った。
芋のとこだけほじって食べようとする子どもの姿に、幼い自分が透けてみえたような気がした。
色づいた葉が庭の隅に降り積もり、かさこそと音を立てて冬の訪れを知らせている。
Writer
- 松塚 裕子
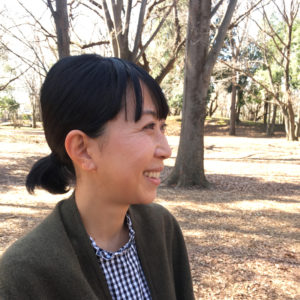
-
1981 福岡県出身
2004 武蔵野美術大学工芸工業デザイン科陶磁専攻卒業
2006 神戸芸術工科大学造形学科陶芸コース助手として勤務
2010 調布市深大寺の自宅工房にて制作をはじめる
記憶とともにながく大事にしてもらえるような器を作りたいと思っています - もっと読む
メルマガ登録
最近の投稿
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月


