 連載
連載
作り手による文章の世界
みちくさドライブ
松塚 裕子
台所より
2021.03.25乾いた生ぬるい風がふきわたって、洗濯ものを散らばした昨日は幻だったのか。
今日はダウンジャケットのボタンをぴっちりと上までしめるほどに心底冷える。
慌ただしい日々を抜けて、ぼんやりとした頭で季節のはざまを揺れるように過ごしていたら、いつのまにか庭の水仙はふんわりとほころんで、冬の気配が残る中を、すっと背を伸ばして立っていた。
カレンダーとにらめっこしながら窯焚きを繰り返した毎日が過ぎ去ると、今度はオーブンの中をじっとりと見つめ、鍋のそばにべったりと張り付く日々がやってくる。
今日はドーナツ、明日はスコーン。
父から送られてきた柑橘で、レモンカードや夏みかんのピールも作りたい。
忙しい時期に、この仕事がひと段落したら作ろう、と心の中に溜めておいた妄想料理の数々を実現してゆくのだ。
この期間は、ぎゅっとひと時集中してかたくなってしまった筋肉や脳を意識的に緩めるような、自分にとっての次へとむかう準備体操のような時期なのだろう。
緩めたゴムを再び限界まで引っ張り、溜めた力で球を遠くに飛ばすようなイメージが浮かんでくる。
伸びと縮みは背中合わせの作業なのだとつくづく思う。
鼻先にぶらさげておいたニンジンを、余すところなく味わいつくす、ごほうびのような時間。
台所でなにかしら作っていると、子どもが横から手を出してくるので一緒に作ることになる。
途端に手も机も粉まみれ、作業の手順もすっ飛ばし、何かを入れ忘れるのだってしょっちゅうのこと。
仕事はひとりでもくもくと計画通りに進めるが、おやつ作りは誰かとおしゃべりしながら、ちょっとくらい思い通りにいかなくても、出来上がりが不細工でも、楽しくておなかが満たされれば大成功。
でも、クッキーを焼くときは気を付けなければならない。
仕事での窯焚きが続いた後に焼くと、かなりの高確率で失敗する。
焼成で縮むやきものと違って、クッキーは焼くと膨らむので、ある程度の間隔を保って並べなければならない。
そう、ソーシャルディスタンスが重要。
そこをすっかり忘れて、器の窯詰めをするときと同様に、クッキー同士の隙間をかなり詰めてぴっちりと並べて焼き、全部くっついて出来上がるという失敗を何度も繰り返している。
楽しみにオーブンをのぞいた時、私の意に反して膨張し一枚の板と化したクッキーを見て、ああまたやってしまったとうなだれる。
しかしそれもまた一興、割って食べればいいじゃないかとすぐに切り替えられるのだが。
やきものの窯出しがこうだったら、きっとしばらく立ち直れないだろう。
こんなとき、焼くという工程の不思議さを思う。
一度自分の手の届かないところへと手放したものが、再び姿を変えて戻ってくる。そこには、私が予想していたこと、思いもよらなかったこと、失望、安堵、期待、多くの感情が詰まっている。
それらすべてが、ないまぜになって自らの手元に再び帰ってくるとき、私にできることはただひとつ、まずはそのままを受け入れることだけなのだと毎回思う。
心をかけて手放し、そして新たなものを受け入れる、その繰り返しのなかにある途方もない難しさを知る。
少し大げさかもしれないが、私はいつもこの行為に人生の在り方のようなものを感じている。
やきものは、器として使える状態になるまでにいくつもの工程を越えねばならない。
成形でうまくいっても、乾燥で割れ、素焼きで割れ、釉薬がけで失敗し、ようやく生き残ったものも最後の焼成でだめになったりする。
ずいぶん長い道のりだなあと途方にくれることもあるし、先に何があるとも知れぬ道のない旅のようだと思うこともある。
けれど、それをはるかに越える、たましいがふるえるような喜びや、深く満たされるような瞬間に出会うことがある。
だから続けているのだと思う。
それにしても、やきものの窯がもしもオーブンみたいに中を観察できる仕組みだったら、焼成中はおそらく窯の前からは離れられなかっただろう。
ああ、釉薬が溶けすぎている!形がゆがみだした!今すぐ取り出したい!と大騒ぎだったろうから、見えない仕組みになっていて本当によかった。
仕上がりの電子音がピーっと鳴って扉をあける。
よかった、今回はうまく焼けたみたい。
本日のおやつは、台湾カステラ。
湯気とともにまん丸に膨れたお月さまのような姿でオーブンから現れた。
ふんわりふくらんだお菓子を目の前にして子どもの喜びが見えるとき、心の底から嬉しい。
家族や友人とその喜びを分け合い、互いに美味しい気持ちを共有できることの幸せ。
つくることが純粋に誰かの喜びにも繋がると日常の中で実感できるひとときは、大きな支えであると思う。
ひとり器にむきあうとき、そして誰かと美味しい喜びを分かち合うとき。
そのはざまを、行ったり来たりしながら、これからもゆらゆらと泳いでいく。
自分だけの道を探しながら。
湯気でくもった窓から見た庭は、少しずつ見え始めた小さな春の兆しを抱きとめるように、明るい光で満たされていた。
Writer
- 松塚 裕子
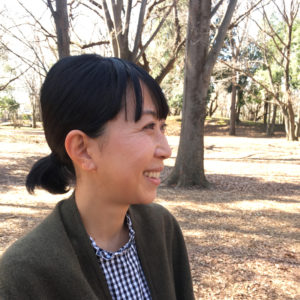
-
1981 福岡県出身
2004 武蔵野美術大学工芸工業デザイン科陶磁専攻卒業
2006 神戸芸術工科大学造形学科陶芸コース助手として勤務
2010 調布市深大寺の自宅工房にて制作をはじめる
記憶とともにながく大事にしてもらえるような器を作りたいと思っています - もっと読む
メルマガ登録
最近の投稿
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月




