 連載
連載
作り手による文章の世界
みちくさドライブ
松塚 裕子
レモンの木
2022.04.032月も終わりに近づくころ、毎年福岡の実家から段ボール箱にぎっしりと詰まった柑橘類が送られてくる。
箱を開けると、ピカピカのまぶしさで顔を出すレモンや夏みかん。
冬、コロナ禍のはざまに久しぶりに帰省した。
裏庭にあるレモンの木は、あらためて見るとかなりの大木になっており、すこんとぬけるような青空に向かって枝葉をのばして立っていた。
この木がここへやってきたのは、たしか20年以上前のことだったか。
週末になると、夫婦で近所のホームセンターに出かけては、花や肥料を買い込んでせっせと庭仕事に勤しむ両親を横目に、なにがそんなに楽しいんだろうと思いながら友人らと出かけていた私はたぶん高校生くらいだったろうか。
そんな自分も、いまや夫と一緒に、かつての両親と同じような週末を過ごすようになっているのだから不思議なものである。
やってきたレモンの木はまだひょろひょろの頼りなさげな苗木だった。
存在を忘れるほどの影の薄さで、実をつけない時期がずいぶんと長かったように思う。
日の光がさんさんと当たる、庭の一等地に植えられても、うんともすんとも言わないまま7、8年が過ぎた。
私もそのころにはとうに家を出てしまって、レモンの木の存在なんてすっかり忘れ去っていた。
両親のあいだに「もう、切っちゃおうか」なんて話がでるようになった年に、ようやく一粒実ったそうだ。
長い沈黙を破るように実をつけた木は、そこから毎年実を増やし続けた。
よく生る年、少ししか生らないけど芋のごとく大きな実をつける年、収穫間近、突然の雹にうたれてたくさん傷のついた年。
台風で枝が大きく折れた時もあったと思う。
今年は、小粒ながらも200粒以上の実をつけたようだ。
40歳をむかえた昨年、体調不良の波があった。
体重が落ち、地に足が踏ん張れないようなふわふわとした居心地の悪さが常にあった。
それに伴い体力と気力もがくんと落ち込み、こりゃあまずいぞと思いながらも、ずぶずぶと沼にのまれるように心身が思い通りに働かない重たい日々が続いた。
歳を重ねるにつれて経験も知識も増えてゆくけれど、体力は確実に衰えてゆく。
私はいまちょうど、分岐点のようなところにいるのかもしれない。
これまで当たり前にできたことがままならない、もうひと踏ん張りで踏ん張り切れない。
今までと同じやり方ではきっともうだめなのだ。
何かを変えないと。
そして心機一転、筋肉を鍛えようと思い至った。
自分の身体を強くすることで乗り越えられることがあるのではないか。
鍼灸師の友人に勧められた四股ふみトレーニングなるものを、毎日やることにした。
大きな筋肉が集中している下半身を効率よく鍛えられるらしい。慣れてきたらスクワットも加えてゆく。
今までの人生に全くなかった、筋肉を鍛えるという新しい扉が40歳にして開いたのである。
日課としての筋トレが生活に根付いたころ、面白い変化が現れた。
明らかに疲れにくい、のである。
何をするにも、常に少しだけ身体のなかに余力がある。
それは生活だけではなく制作の中でも実感することができた。
ろくろを挽く際は、座ってやや前傾姿勢になるのだが、以前よりも身体の軸が安定したせいか、動作に安定感が増してとても楽に挽けるようになった。
大きめの立ちものなどは、いくつか作ると疲れてしまっていたけれど、すいすいといつまでも作っていられるような気にさえなる。
ふと頭のなかに、「心技体」という言葉が浮かぶ。
制作を続ける中で、心を見つめ技術を磨くことには力を注いできたが、体に関してはどうだっただろうか。
健康に気を遣うという意味では気にかけてきたつもりだが、おおよそ現状維持程度で、積極的に鍛えることはしなかった。
失ってゆくものの中で見つけた新しい実り。
それは確かな実感をともなって私の内側にすとんとおりてきた。
奥底からひたひたとみなぎる底力のようなものが、ちいさな自信となって芽生えた出来事であった。
実家で、父は相変わらず庭にいた。
カーテンの様に咲き乱れるランタナ。
小さな畑とブルーベリーの木。クリスマスローズもじきに満開になるだろう。
緑のなかにうずもれるようにして、ひとり手入れをする父を見ながら、ここに流れた時間を思う。
いろんなことがあった。
あんなひょろひょろの木が、見上げるほどの大木になるのだから、私も立派なおばさんになるわけだ。
たくさんの実りをもたらした木は、ずいぶんとおじいちゃんの風情が漂ってはいるが、しっかりと大地に根をはって堂々とした佇まいで立っている。
雨も嵐も日のあたたかさも、時間も、すべてをその身に受け止め続けて、ただ静かに。
午後のほんのひととき差し込んだ日差しが、庭全体をすっぽりと包み込んでいる。
ここにちりばめられた命の粒ひとつひとつを祝福するかのように、光は隅々まで明るく照らし、やがてまた移ろいでいった。
私はまるで庭の一部にでもなったみたいに、いつまでもその様子を眺めていた。
Writer
- 松塚 裕子
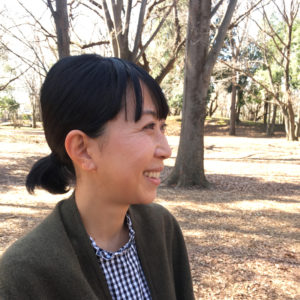
-
1981 福岡県出身
2004 武蔵野美術大学工芸工業デザイン科陶磁専攻卒業
2006 神戸芸術工科大学造形学科陶芸コース助手として勤務
2010 調布市深大寺の自宅工房にて制作をはじめる
記憶とともにながく大事にしてもらえるような器を作りたいと思っています - もっと読む
メルマガ登録
最近の投稿
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月



