 連載
連載
作り手による文章の世界
みちくさドライブ
松塚 裕子
わたしの風景
2022.12.09寒くなると思い出すのは、父が着ていたセーターの色。
苔みたいな深い緑色、濡れた土のような暗い茶色やベージュ。
みっしりと編まれたセーターは触るとすこし硬くて、ずんぐりとした背格好の父が着ると、なんだか巣ごもりをする熊のように見えたものだ。
肘をついて机に向かう仕事が多かったせいで、そこだけ擦り切れて薄くなってしまうので、母にスウェードでできたあて布のようなものを付けてもらっていたような気がする。
土曜日の昼に学校から帰って玄関を開けた瞬間、家の中にうっすらと煙草のにおいが漂っているときはたいてい父が家で仕事をしており、私はそういう日がなんとなく好きだった。
母が料理をする台所の音を聞きながら、父の仕事の傍らでこたつに入ってテレビを見たり、漫画を読んだりだらだらと過ごしていただけなのだが。
そんななんて事のない瞬間から、きっと大きな安心をもらっていたのだろうと思う。
今でも、冬に家の中で過ごす時間がとても好きだし、誰かが仕事や作業をしている横にいると妙に落ち着く。
秋から過ごしやすい陽気が続き、薄着で油断していたらここ数日でぐっと冷え込んできた。
厚手のセーターを引っ張り出し、預けっぱなしで忘れていたコートを慌ててクリーニングから引き取りに行った。
外に出ると、ぎゅっと毛穴がしまるような冷たい風にさらされる。
ぐるぐるにマフラーを巻いて、ついでの買い物を済ませて家へと急ぐ道すがら、ご近所の家から夕餉の支度の気配が漂ってくると、無性にグラタンが恋しくなる。
ぽってりと濃いクリームを欲するようになると、いよいよ冬も本番かなと思う。
うちのグラタンは、鶏、マカロニ、玉ねぎ、きのこ、エビなどが入っている別になんのことはない、普通のものだ。
ときどき気まぐれに牡蠣やカリフラワーなんかを入れてみたりもするけれど、結局基本に戻る。
この時期のグラタンはやっぱりちょっと特別だなあと思う。
平和そのものといった、あの穏やかな色。
ぐつぐつとチーズの溶ける表面からは一見何が入っているのかわからない。
チーズの層を越えて食べ進めるうちに、ホワイトソースの衣をふんだんにまとった具に出会う楽しさたるや、まるで宝探しのようじゃないかと心躍る。
穴の開いたマカロニの形状も良い。
小学生の頃によく読んでいた、「こまったさんのグラタン」という本の影響もあってか、昔も今も変わらずに好物である。
グラタンのときに使う皿は、私が子供の頃から使っているもので、母が亡くなったときに実家からもらってきた。
おそらく、両親の新婚時代に買ったものだろうから、もうかれこれ40年以上は経っている。
割れもせず、たいした汚れもつかず幾度となくオーブンに入れられて、時には焦がされたりもしながら世代を越えてうちのグラタンの歴史を支え続けてきた。白地に茶色のラインが入った昭和80年代に作られたであろうその耐熱の器、どこのものだろうと思って調べてみようかとも思ったのだが、なんだか無粋な気がしてやめてしまった。
今でも取り出すたびに、少し母を思う。
そして夕飯のメニューに胸ときめかせた子どもの時間を。
冬のにおいと、父のセーターとグラタンの湯気を。
記憶の中には、色がある。
色とにおいと手触りと、つかめない空気の欠片のようなものが時を経ても身体のなかにふよふよと漂っており、普段は忘れているのにふとしたことがきっかけで、まるで砂粒がさらさらとこぼれおちるように現れる。
私の日常はいたって平凡に過ぎてゆく。
朝、子どもを幼稚園に送り、家事と仕事をして、子どもを迎えに行く。
公園に寄り、近所の野菜売り場をのぞき、夕飯に何を食べようかと考える。
夕暮れ時に、洗濯物をとりこみにベランダに出ると、西の空は何ともいえない色で夜の準備を始めている。
今日も一日が終わるなあと安堵の気持ちで空の移り変わる様子を眺めている。
木々は色合いを変えていっせいに葉を落とす。
流れるように過ごしてしまうけれど、その中でも心が震えるような瞬間は確かにあって、それは静かにゆっくりと自分の中につもっているのかもしれない。
ずいぶん時間が経った後、かけがえのない日々としてまた思い出すときが来るのだろう。
歴史の研究を生業にしていた父が言っていた。
年表にのるような大きな出来事の傍らには、数え切れない名もなき人たちの日常があって、それは点のように小さなものだけど、それらが無数に繋がって線になり今に続いているのだと。
歴史と言えば年号の暗記、テスト前の付け焼刃的な学び方しかしてこなかった私だが、その言葉は不思議な重みをもって自らの内に残った。
帯のように連綿と続く流れのなかに、小さな粒の如き自分も身を置いていると思えたからだろう。
戻らない愛おしい日々の空気を時折感じながら、今目の前に触れることのできる日常を生きる。
大きな循環のなかの点のような私の日々も、いつか遠くから見たときにひとつの風景を成すだろうか。
Writer
- 松塚 裕子
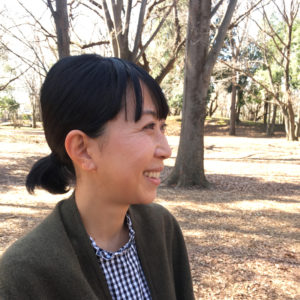
-
1981 福岡県出身
2004 武蔵野美術大学工芸工業デザイン科陶磁専攻卒業
2006 神戸芸術工科大学造形学科陶芸コース助手として勤務
2010 調布市深大寺の自宅工房にて制作をはじめる
記憶とともにながく大事にしてもらえるような器を作りたいと思っています - もっと読む
メルマガ登録
最近の投稿
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月



