 連載
連載
作り手による文章の世界
みちくさドライブ
松塚 裕子
ひとしずくのその先に
2020.07.23鈴なりを夢見て植えた庭の小さな金柑は、今年は一粒も実を付けなかった。
新しい環境に慣れるまではもう少し時間がかかるのかもしれない、
そう思っていた矢先に近所の直売所に小ミカンの実が売っているのを見つけた。
大きさも見た目も金柑にそっくりのそれは、ひとくちかじれば身が縮むほどに酸っぱくて、不思議と皮のほうが甘かった。
野菜と一緒にマリネにしたり、ジュースに肉や魚を漬け込んだりと、じゅうぶんに楽しんだのち、ふと思いついてジャム名人の友人に送ったら後日素敵なレシピを作って教えてくれた。
鍋のなかいっぱいに、おひさまの光をとじこめたみたいな、こがね色のジャム。木べらでまぜるたびにきらきら光っている。
とうめいな果実は粒つぶの大きな宝石のよう。
ひとさじ掬って口に運ぶと、季節の香りをぎゅうぎゅうに閉じこめた濃い味わいがした。
これまで、ジャムというものは本など読みながら弱火で気長にじっくり煮る、のんびりした食べ物だと思っていた。
ことこと煮て、柔らかくした果物の砂糖煮といったところだろうか。
けれど友人のレシピで作ったそれは、私が今まで作ってきたものとは全くの別物だった。
果実が本来持っている風味を損なわないように砂糖の量を見極め、果肉がほどける柔らかさに火を入れながらも、香りをぎゅっと閉じ込める。
決して長く火を入れすぎて香りをとばしてはならない。
これは、本など読みながらなど到底できぬ。
旬の果物のいまいちばんいいところをいかに凝縮して閉じ込めるかどうか、私にとっては揚げ物にも匹敵する瞬間勝負の食べ物だった。
いままで自己流で作ってきた慣れ親しんだ食べ物に秘められた、奥深き新しい世界を知った。

ちょうどそのころ、窯たきでの失敗が続いていた。
今まで作ってきたものが、どうにもうまく焼けない。
器の表面はぼつぼつと穴が開き、鮮やかだった色はくすみ、つるりとした釉薬は剥がれ落ちて無残な状態で窯からでてくる。
作り方は何も変えていない、温度だって焚き方だっていつもと同じなのに、いったい何が起こっているのだろう。
ざわざわとした気持ちに蓋をして、とにかくひとつずつ今までのやり方を見直すことにした。
釉薬を作り直し、土を変え、窯の温度計の故障を調べたがいっこうに改善しない。
相変わらず肩を落とすような窯出しが続いた。
これでだめならもうわからない、というところで窯焚きの温度、時間をいちどすべて組みなおそう、と思ったときにようやく光が見えてきた。
何事もなかったかのようにきれいな顔をした器が出てきた夜は、ひさしぶりに穏やかな気持ちで眠ることができた。
私の使っている電気窯は、独立したときにはじめて買ったもので、今年で10年目を迎える。
丁寧に調べてゆけば、設定温度は同じでも熱の伝わり方やカロリーのかかり方は以前とはずいぶん変わっていたことがわかった。
電熱線の摩耗なのだろう。
見た目にはわからなくとも、たくさん使っていれば傷んでくるのはあたりまえだ。
私だって、10年の間に、シミもシワも増えているんだから。
なぜ何もかわらない、なんて思っていたのだろう。
土も、釉薬に使う原料も自然のものなのだから、永遠に同じ状態だなんてありえないことなのだ。
窯の状態も然り。
電話の一本、メールのひとつ、スイッチひと押しで手にすることのできていた当たり前のなかで、そんな大事な感覚がいつの間にか麻痺してしまっていたことを恥ずかしいと思った。
けれど、長年慣れ親しんだやり方を一旦手放して、新しい方法を見つけようとするなかで、自分の心のうちになにかしらの清々しさも感じていた。
この色はもう作れなくなってしまうかもしれないけれど、これを失ったからといって自分にとってほんとうに大事なものはなくならないだろうと思えたことは、なんだか心強かった。
芯の部分がよりくっきりと見えたような気がしていた。
変わってゆく世界の中で揺れながらも、手放してもいいもの、大事にもってゆきたいもの、その手ざわりを確かにして新しい自分をつくってゆければいいのだろうと思う。
これから先もきっと、自分のなかのあたりまえ、は変わってゆくだろう。
いつも携えていたいものは、揺らいでも迷ってもきちんと前に一歩ふみだしてゆける足なのだ。
あたりまえの世界から少しだけ外にでると、凝縮したジャムみたいに鮮やかな驚きに出会えることだってあるのだから。
春先にめずらしい大雪が降ったなあと思っていたら、いつの間にか梅雨。
長雨があけたら、また川に遊びにいけるだろうか。
暑い日差しの中でひんやりとした水に足を浸す瞬間は格別なのだ。
うつりゆく季節の中で、その形を自在に変えながらも、とうとうとながれてゆく水のなかに立っていると、不思議と自分もその一部になったような気がする。
しなやかにさらさらと流れてゆく川が自分の体のなかにも欲しいと思う。
きらきらのジャムをひとすくいパンにおとして庭に目をやると、さっきまで降っていた雨がやみ久しぶりの晴れ間がのぞいた。
ノウゼンカヅラが雨粒を受け止めて咲きほこっていた。

Writer
- 松塚 裕子
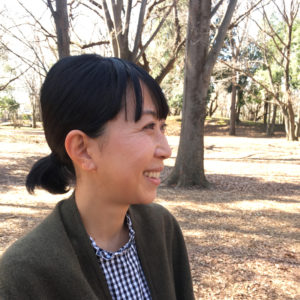
-
1981 福岡県出身
2004 武蔵野美術大学工芸工業デザイン科陶磁専攻卒業
2006 神戸芸術工科大学造形学科陶芸コース助手として勤務
2010 調布市深大寺の自宅工房にて制作をはじめる
記憶とともにながく大事にしてもらえるような器を作りたいと思っています - もっと読む
メルマガ登録
最近の投稿
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
